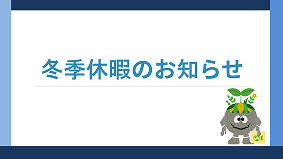お知らせ
②再生砕石に関する共同研究について、広島大学河合教授と黒姫グループ代表にインタビューを行いました。
【対談シリーズ2】黒姫と広島大学との共同研究について聞く
脱炭素に貢献する再生砕石「CO₂-Nomicom®」
世界的に進む脱炭素社会への転換。2050年カーボンニュートラルの実現は、地球規模の課題です。
2021年気候サミットにおいて世界に向けてこれを宣言した日本では、途中経過である2030年の野心的目標達成も含めた脱炭素への挑戦を継続していく必要があります。
黒姫グループが製造する再生砕石「CO₂-Nomicom」(RC-40)は、脱炭素に寄与する新たな付加価値を持つ建設廃棄物(コンクリートがら)リサイクル材料として注目されています。
前回の対談では、広島大学 河合研至教授と黒姫グループ代表取締役 唐澤明彦が共同研究に至った経緯を伺いました。
共同研究は「再生砕石がCO₂を吸収固定化する化学的メカニズムの解明」「CO₂吸収固定量を最大化するための技術開発」「吸収固定化されたCO₂量の分析方法の高精度化」を主たる目的として実施していますが、今回の対談では再生砕石にあまり詳しくない方にも共同研究の内容が分かるように、黒姫グループ広報課の玉木がお伝えしていきます。

話し手
河合 研至
広島大学 教授 大学院先進理工系科学研究科
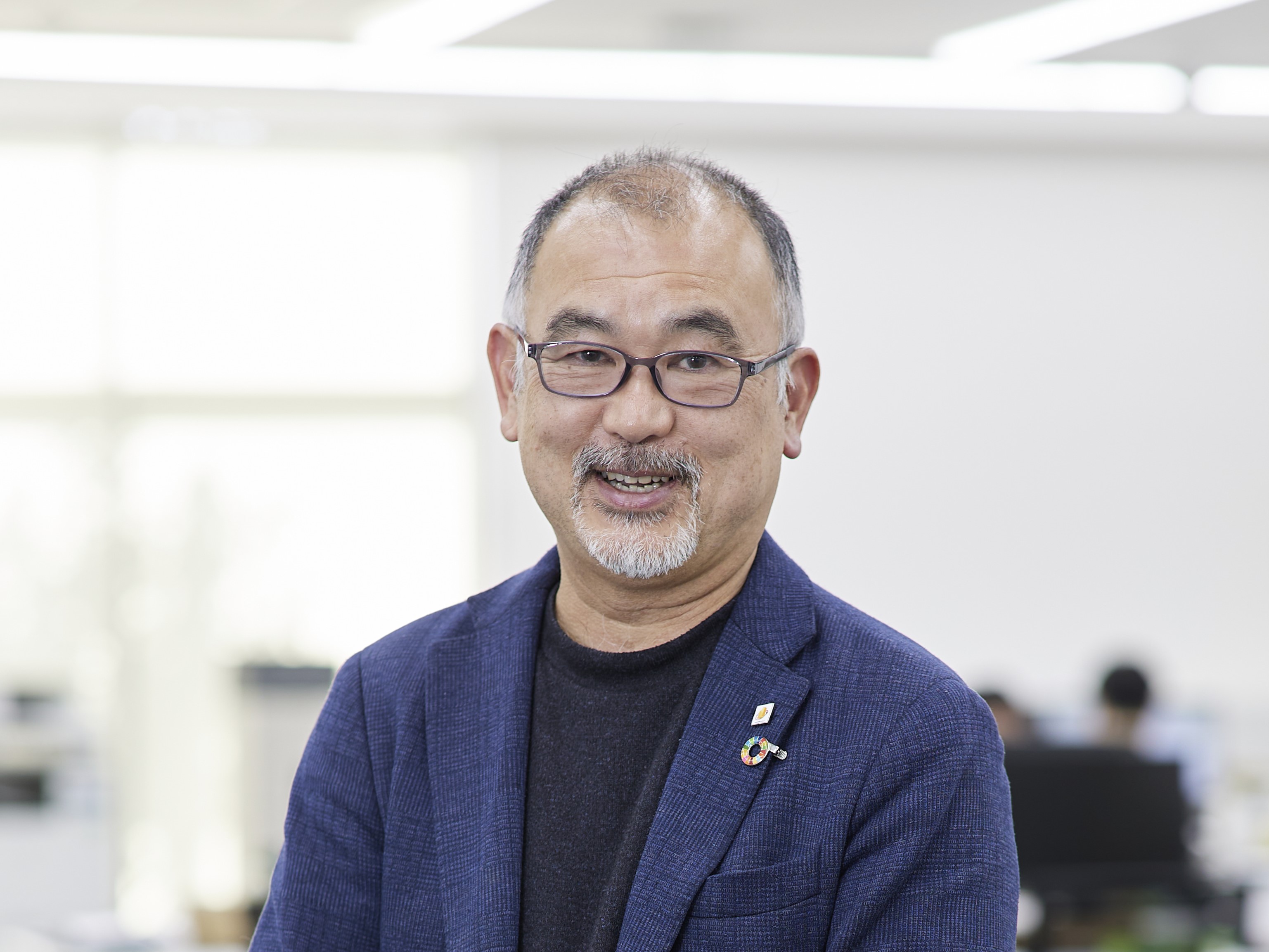
話し手
唐澤 明彦
黒姫グループ 代表取締役(株式会社黒姫・広域環境開発株式会社・埼玉総業株式会社)

聞き手
玉木 美奈
株式会社黒姫 人事広報課
再生砕石と天然砕石の違い
 玉木
玉木
まず、黒姫グループが製造している再生砕石は、天然砕石に比べて環境面や経済面でどのような利点があるのでしょうか。
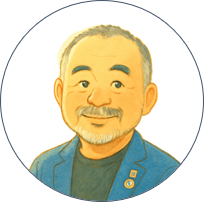 唐澤社長(以下、唐澤)
唐澤社長(以下、唐澤)
利点は、主に五つあります。
これらの利点の内、黒姫グループが製造する再生砕石は、一般的な再生砕石に比べて大幅に大きなCO₂吸収固定能力があるため、黒姫グループの再生砕石を「CO₂-Nomicom」という商品名で販売しています。
利点の第一は、自然環境保全です。天然砕石は、鉱山を採掘して製造しますが、その過程で自然破壊は避けられません。一方、再生砕石はビルや橋などのコンクリート構造物の解体現場で発生したコンクリートがらを原材料とするため、自然環境への負荷が小さいという利点があります。
第二に、資源循環です。都市再開発で発生したコンクリートがらをリサイクルして、再び都市開発の道路路盤材や建築基盤材等に使用することで資源循環につながります。天然砕石の一方通行の使われ方とは異なります。
第三に、CO₂削減です。再生砕石自体がCO₂を吸収固定化する性質を持っています。また、首都圏での市場において、再生砕石は天然砕石と比べて輸送距離が短くダンプカー輸送のCO₂排出量が少ないといえます。
具体的に都内の現場でいえば、天然砕石は栃木県や埼玉県などの山間部から大型ダンプカーで都内まで運ぶことになります。輸送距離は100~150kmほどあり、その間に大型ダンプカーから発生するCO₂はかなり大きな量になります。その点、再生砕石の場合、都内や隣接県のリサイクル工場からの輸送距離は10~30kmほどで、輸送時のCO₂排出量は天然砕石と比べてかなり小さくなります。
第四に、経済性です。天然砕石は採掘・破砕・輸送工程のコストが製品コストに反映されますが、再生砕石は、それらの工程のコストを低減できるため、現在製品コストは天然砕石の1/3程度で市場に供給されています。
最後に、社会的意義です。再生砕石で貢献できる環境負荷低減・資源循環・CO₂削減・経済性は地球・地域・行政・工事発注者・材料利用者にとっても大きな価値があり、その社会的意義は大きいといえます。
CO₂吸収固定のメカニズム
 玉木
玉木
再生砕石を利用することには、様々な利点があるのですね。
では、そもそもなぜ、再生砕石はCO₂を吸収固定化できるのでしょうか。
 河合教授(以下、河合)
河合教授(以下、河合)
再生砕石の構成材料には、コンクリートに使われていた「天然の骨材」以外に、コンクリートに使われていた「モルタル(セメント+砂+水)」があります。
モルタルは、セメントと水が化学反応して硬化したものです。専門的な話になりますが、その化学反応の際に生成される物質は、水酸化カルシウムやカルシウムシリケート水和物と呼ばれるものです。
再生砕石の化学成分としても水酸化カルシウムやカルシウムシリケート水和物が存在します。再生砕石のこれらの成分が大気中のCO₂と反応すると、炭酸カルシウムという物質に化学変化し、これによりCO₂を安定的に固定します。
これは、天然砕石にはない化学的性質であり、再生砕石特有の価値といえます。
研究成果-粒度分布とCO₂吸収固定量の関係
 玉木
玉木
再生砕石には、もともと化学反応によってCO₂を吸収固定する性質があるということですね。2024年度には、このメカニズムを活かしさらに深く研究されたと伺いました。その研究からどのようなことが分かったのでしょうか。
 河合
河合
今回の共同研究の目的は、再生砕石がどれだけのCO₂を吸収固定できるポテンシャルがあるのかを知ることにあります。
研究では、再生砕石製造直後(コンクリートがら破砕直後)と56日間の屋外暴露後で比較し、どれだけのCO₂を吸収固定するかを測定しました。測定は、粒度分布の異なるいくつかの実製品とともに、粒径や粒度分布を意図的に調整した試験体において行いました。
コンクリート構造物として使われている時にもCO₂は吸収固定されています。このことをコンクリートの中性化(炭酸化)といいます。
このCO₂吸収固定量は、コンクリートの配合や環境条件によって異なります。
このことから、コンクリート構造物を解体したコンクリートがらはすでにCO₂を吸収固定しているものの、再生砕石のCO₂吸収固定量の分析においてはこの部分のCO₂吸収固定量は除外します。
そして「コンクリートがらを破砕して再生砕石を製造した直後」から「出荷までの期間(56日後)」までに吸収固定されたCO₂量を分析することになります。
2024年度の研究の結果、黒姫グループの再生砕石「CO₂-Nomicom」においてコンクリートがらのCO₂吸収固定量は12.0kg-CO₂/t、再生砕石製造56日後のCO₂吸収固定量は31.1kg-CO₂/tとなり、この間のCO₂吸収固定量は19.1kg-CO₂/tであることが分かりました。
一方で、国土交通省国土技術政策総合研究所が実施した全国調査における45都道府県の46工場の再生砕石でのCO₂吸収固定量は8.5kg-CO₂/tでした。
このことから、再生砕石「CO₂-Nomicom」は、一般的な再生砕石に比べて約2.3倍のCO₂吸収固定量があることが分かりました。
また、研究からは、再生砕石において小さな粒径ほどCO₂固定能力が高く、特に2.5mm以下の粒径でこれが顕著なことが分かりました。
これは、粒径が小さいほど粒子の比表面積が大きく、より多くのCO₂と化学反応が起こるからです。
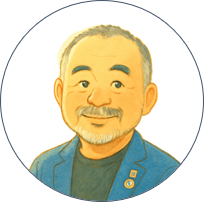 唐澤
唐澤
再生砕石の品質規格には、粒度範囲の幅があります。
黒姫グループが製造する再生砕石「CO₂-Nomicom」は、この粒度範囲の中で、各粒径を品質規格内の最も細かい粒径に調整しています。このことによりCO₂吸収固定能力を高められていることが、今回の研究結果からも分かりました。
ただし、CO₂吸収固定能力を高めるために細粒分を大量に混ぜればいいというわけではありません。
再生砕石には、粒度分布だけではなく、耐摩耗性や支持力、吸水による強度低下の品質規格がありますので、これをすべて満足することが前提です。
品質規格を満たした上で細粒分を最大化すればCO₂吸収固定量を増やせるはずです。
もしくは、CO₂吸収固定量を増やすための別の手段があるのか、そのあたりは2025年度の共同研究でさらに深く追求していくつもりです。
これが叶えば、再生砕石「CO₂-Nomicom」のCO₂吸収固定量は、さらに高いレベルを目指せるはずです。
 河合
河合
粒径をさらに調整したり、再生砕石以外のCO₂吸収固定能力が大きい物質を混ぜてCO₂と反応させることなどで、CO₂吸収固定能力をさらに高いレベルにすることはできると思います。
CO₂固定量を定量化して提供する意義
 玉木
玉木
CO₂吸収固定量の増加は、再生砕石の環境面でのさらなる付加価値向上に繋がりますね。今回の共同研究により科学的根拠を得た今、CO₂吸収固定量を定量化して外部公表することで、黒姫グループとしてどのような役割を果たしていくべきでしょうか。
 河合
河合
科学的根拠に基づいた数値を示すことで、社会に対して再生砕石がどれだけ環境に貢献しているかを明確にできます。
黒姫グループだけでなく業界全体での環境価値を可視化できれば、建設業界の社会的評価も高まると思いますね。
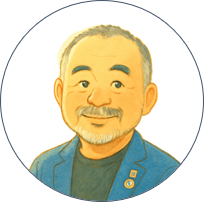 唐澤
唐澤
世界のCO₂排出量のうち建築物関係は37%を占めています。
これまで注目されてきたのは、「オペレーションカーボン」(建物の運用期間に排出されるCO₂)でした。空調効率や省エネ機器の導入による削減努力は進んできましたが、削減余地は限られています。
一方で、近年、新たに重要視されているのが「エンドボディドカーボン」(建設、改修、解体などのライフサイクル全体で排出されるCO₂)です。
黒姫グループの取り組みは、都市再開発におけるLCA(ライフサイクルアセスメント:建築物を構成する各部材・設備の製造・施工・使用・解体に至るまでの建築物のライフサイクル全体おいて発生するカーボンを算定・評価)の推進に直結します。
都市再開発における建設基盤材や道路路盤材として使用される再生砕石でのCO₂吸収固定量を定量化して外部公表していくことで、建築物外構のLCA推進、ひいては都市再開発エリア全体のLCA推進を図ることを目指していきたいと考えています。
インタビューを終えて
 玉木
玉木
今回の対談を通じて浮かび上がったのは、再生砕石の持つ多面的な価値と、それを科学的に裏付ける研究の重要性です。環境保全、資源循環、CO₂削減、経済性を兼ね備えた資材は、循環型社会やカーボンニュートラルの実現に欠かせません。
黒姫グループと広島大学の共同研究は、単なる研究開発にとどまらず、建設業界全体の未来像を形づくる取組みであると思います。科学的な裏付けを得た今、再生砕石に新しい価値が生まれています。そして、それが再生砕石「CO₂-Nomicom」なのです。
循環型社会やカーボンニュートラルの実現に向けて、一歩一歩の積み重ねがこれからの未来の変えていくのだと思います。今回の対談が、再生砕石の価値について多くの方に知っていただけるきっかけになれば幸いです。
2025年度の研究内容についても時期が来たら、みなさんにお伝えできればと思います。


 お問い合わせ
お問い合わせ
 メニュー
メニュー 閉じる
閉じる